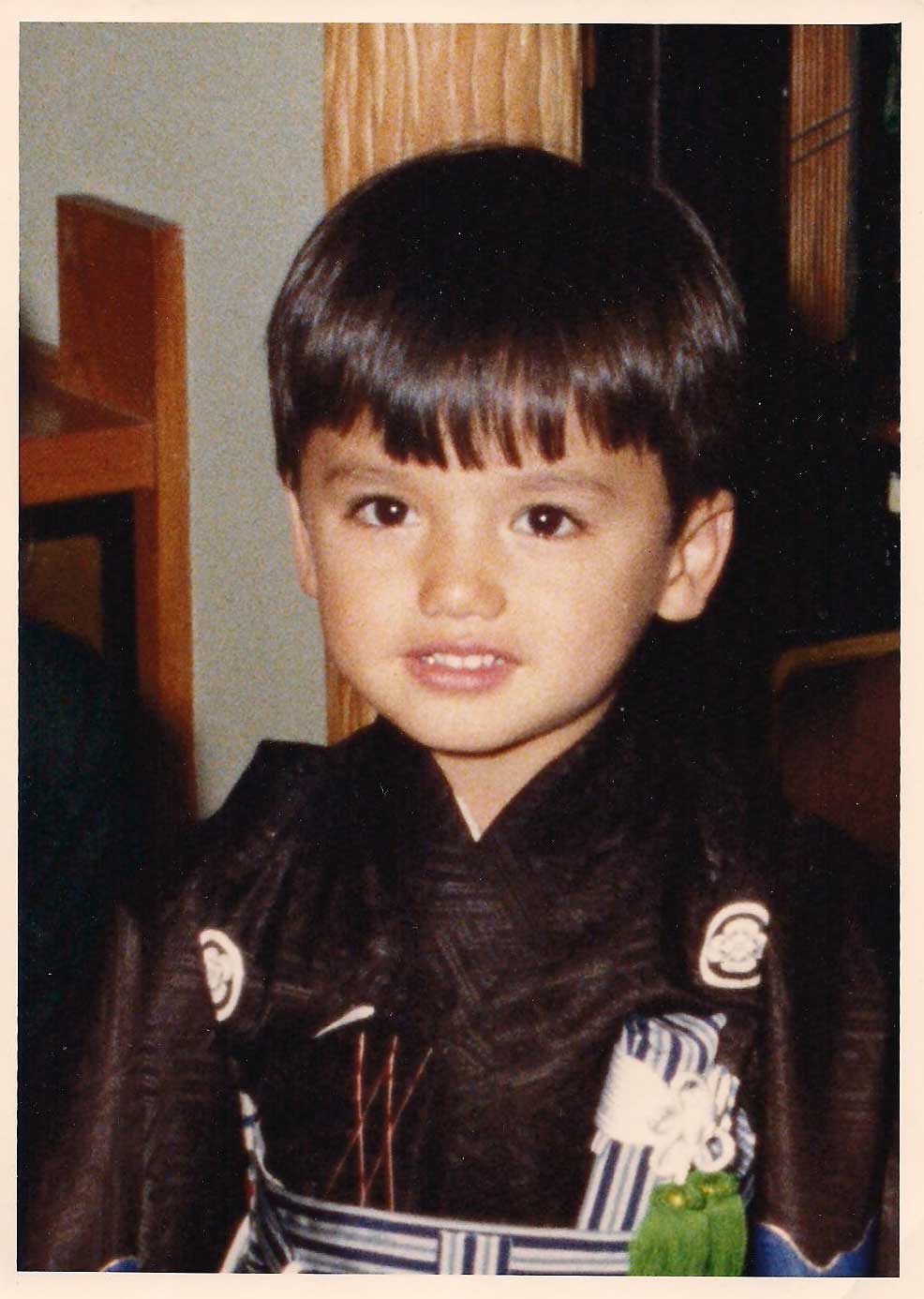恋女房いや今はもう古女房となってしまったが、いつか彼女との馴れ初めというか出逢いを話さなければと思ってきた。私の人生のドラマの中でこの愛すべきパートナーの果たす役割は、今も昔もそしてこれからも主演女優であることに変わりはない。アメリカ生活が長くなったせいか私は自分を売り込むことに何ら躊躇もしなくなった。だからこの話もたぶんに独善と偏見に満ちたものになるだろうが、その辺りはご容赦願いたい。
男と女の出逢い、100組のカップルがいれば100組のユニーク溢れる恋物語がある。私達のケースもまたしかり、遠い昔日のこととなってしまったとは言え、あの頃の甘美な想い出は今尚鮮烈に私の脳裏を横切ってくる。
コロラドはロッキー山脈の山奥、そこでのカウボーイ生活が私のアメリカでの足跡の第一歩である。35年も前の話である。数年後を経ていっぱしのカウボーイになったところで彼女と巡り会った。フロリダのディズニーワールドで働いていたが、たまたま米国陸軍の諜報部に志願をし受理された。父親が海軍の艦長だったのでその影響もあったのだろう、鼻っ柱の強いじゃじゃ馬ではある。入隊する前に半年間の余裕があったのでその間を利用し以前から興味のあった西部の観光牧場での短期の仕事をゲット、やってきたのが私が働いていた牧場だったのである。
春になると観光シーズンで従業員も膨れ上がる。仕事柄若物が殆どで全米各地から集まってくるのだが50名前後のうちで8割がピチピチした若い女性で占められていた。だから私も毛色が違っていたとはいえ需要と供給の関係も手伝ってよくもてた。決してハンサムとは言えない私だが、人生後にも先にもこの時ばかりは百分の一くらいに縮尺された光源氏になったような気がしたのである。時代は変われどもカウボーイは都会からやってくる娘達にとっては興味尽きない対象であったし彼女もそのワンオブゼムであった。
初めての紹介を受けた時、お互い数秒間見詰め合って時間が止まった。突然、訳の分からない衝撃が走ったのである。ああ、この女と一緒になりそうな気がすると運命的なものを感じたのだ。聞けば彼女も似た様な戦慄を覚えたと言っていた。彼女は、私の笑顔に東洋的神秘さを感じ、この変わり者のカウボーイは良いか悪いかは別にしてそのうち何かやらかすのではないかと言うのが直感だったらしい。チャーリーズエンジェルの中のジャクリーンスミス似の彼女は私が長い間夢見てきたこれ以上は望めない女だった。その愛くるしい微笑みに魅了されて私は天にも昇るような気持ちになったのである。
若い人いきれでムンムンしているから毎日夕食後はパーティである。真夜中まで飲んで歌って踊って、そして翌朝5時には起床、お馬さん達の面倒を見るのが日課。若さ故にそんな無茶も出来た。そして山奥の牧場でも一気飲みや早飲み競争があった。図体のでかいアメリカ人に囲まれ埋没気味の私だったが、身長5尺6寸体重16貫500、至って健康、負けず嫌いの特攻隊精神だけは微塵の揺るぎもなかった。小さな身体だったが、学生時代ラグビー部でしこたま一気飲みをやらされたから酒を飲むのは早くそして強かった。ちなみに缶ビールの栓を抜いて飲み干す迄の私の記録は2秒3だったのを覚えている。(一度試してみて下さい。飲むというよりは吸引力の勝負です。)だから時にはチャンピオンになれた。そんな時、私は驚きと優しさが交錯して私を見つめるじゃじゃ馬の目を見逃さなかった。
残念ながら格好よさではやはりアメリカ人カウボーイには叶わない。だから私は積極的に勝負に出た。アメリカでは彼と彼女がステディの関係であるというレベルになればまず他の連中は手を出して来ない、だから如何に短期間にその様な男と女としての振る舞いを周囲に知らしめるかである。朝起きてから夜寝るまで可能な限り彼女の興味を自分に向けさせた。自分の拙い英語がもどかしかったが一生懸命自分の生い立ちや、カウボーイへの憧れ、そして将来の夢を語った。そして二人は赤い糸ならぬ運命的に結ばれるようになっていると徹底的に口説いたのである。そうこうしているうちに、と言っても会ってから僅か二ヶ月程であったが電光石火、私達は牧場の仲間達に二人の婚約を発表したのである。
勿論軽挙妄動と非難ごうごうであったが、私達には確固たる自信を裏ずける出来事があった。彼女が勤め始めて二ヶ月が経った頃、仕事上の行き違いからマネージャーと口論となり首になった。謝ればいいのに謝らない。気の強い女である。彼女は自分は正しいことをしたのに何でこんな仕打ちを受けるのかと悔し涙にくれた。そして、
「 あなたが、”俺の傍に居れ” と言うのであればこの辺りに別の仕事を見つけます、でなければ私はコロラドを去ります。」
今思えばこれが彼女の私に対する精一杯の意思表示だったと思う。勿論私の答えは決まっていた。それから一ヵ月後、私はカウボーイ仲間と麓のバーへ行った時しこたま飲んで飲酒運転をしたのである。ほろ酔い気分で運転しての帰路、何か後ろの方で赤い光がピカピカし出した。これ何事かいなと車を止めると、パトカーからポリさんが降りて来たのである。
「お前さんは飲酒運転をしているな?」
「いや私は正常です。」
「じゃ車から降りて歩いてみせろ。」
「分かりました。」
「真直ぐ歩けないから、飲酒をした証拠だ。」
「私は真直ぐ歩いています。なんならもう一度歩いて見せます。」
「前回より酷いぞ。もう抵抗するのは止めろ。」
訳の分からない外国人がこんな山奥で酩酊している、ポリさんカチンときました。
「お前を引き受ける人が居なければブタ箱にブチ込むぞ。いいか!」
チクショウ、その後には多分強制送還が待っている。ああ俺もこれで万事休すか、
何とかしなければ。。。。
とっさに
「実は親しい女友達がいます。」
「ではそこへ連れて行け。そしてお前が嘘を言っていないか確かめさせてもらうぜ。」